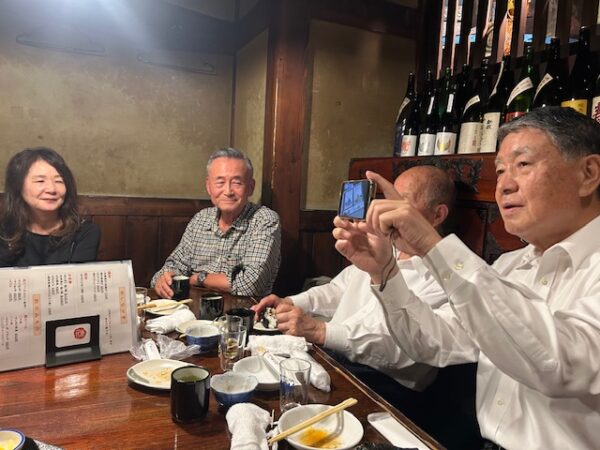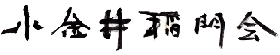早稲田サロン(2025.05.13)
5月早稲田サロンは、去る13日(火曜日)の夕刻、居酒屋「壱番
会長の中田 晃さん (1970 政経 卒)を講師役にお迎えし、「昨今の年金事情」の
タイトル/テーマ(副題:「長寿高齢化と少子化」)で、ご講話い
いつもの第二土曜(10日)から、店舗側の都合で休業明けである
変更したこともあり 日程を勘違いした会員が2名おられ、遅れて途中参加の
1名を加えた 総勢11名が居酒屋の大テーブルを囲んでの 講演となりました。
中田さんは会社在籍中の2001(平成13)年に社会保険労務士
で特定社会保険労務士を付与されて以降、75歳を前にした202
までの十数年間を ネンキンダイヤルオペレーター、総務省 年金記録確認東京
地方第三者委員会調査員として活動して来た まさに「年金マン」と呼ぶにふさ
わしい方です。(尤も某氏などは「カラオケマン」とも呼んでいる
本題は皆さんにとって関心の高いテーマで 「年金マン」の語りに参加者一同は
熱心に耳を傾けながら 2時間余が過ぎ、盛会のうちにお開きとなりました。
本題の講演内容「要旨」を以下、ご報告します。席上配布された資
すが、別途中田さんに詳細を確認し数値・文面を補足した報告内容
1.「年金」の仕組みについて ➡ 「3階建て」で構成されている。
1階 部分: 「国民年金」 ➡ 基礎年金。20歳から60歳までの全国民が加入
2階 部分: 「厚生年金」 ➡ 70歳までの会社員、公務員が加入
3階 部分: 「企業年金」 ➡ 「厚生年金」対象者が独自に加入
2.公的年金の主な歴史
歴史的な「流れ」については、添付「講演資料その1」をご参照下
「厚生年金」は肉体作業労働者を対象にすでに戦前に創設されてい
年金制度の創設当時における受給期間は10年間を想定していたと
「国民年金」創設当時(昭和35年)の65歳男性の「平均余命」
3.「年金」について
① 「厚生年金保険法第1条」の定めるところでは ➡ 「年金は保険である」
本法律は 労働者の老齢リスク・障害リスク・それに死亡リスクへの保健給付
行ない、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与する
とする。以下の災害リスクに見舞われた際に助け合う「共助」の仕
老齢リスク ➡ 老後の生活資金枯渇
障害リスク ➡ 疾病等による就業困難
死亡リスク ➡ 大黒柱を失ったあと残された遺族の生活保障
「障害年金」は国民年金では等級別に1級と2級、厚生年金では3
障害は65歳前に初診日があり納付条件が必要。精神障害が対象と
人工透析は2級扱い。「遺族年金」は、亡くなった人の「厚生年金
支給される。ほかに「国民年金」には「寡婦年金」もある。
② 支給方式は 今現在の現行世代が払った保険料が今現在の受給世代の年金と
して支払われる「賦課方式」が採られている。「国民年金」➡ 2分の1を税金で
負担。「厚生年金」 ➡ 2分の1を会社側で負担する仕組みとなっている。
受給要件として「請求」が必要。原則65歳から支給。但し個々人
より、請求に当たって受給開始時期の「繰り上げ」(最大60歳~
(最大~75歳)の「選択」が可能。因みに「繰り上げ」の場合の
で「最大繰り上げ」のケース(60ケ月)では▲24%、「繰り下
0,7%(月)、「最大繰り下げ」のケース(120ケ月)では+
始める場合、65歳で貰い始める年金の84%増しの金額を毎月貰
後期高齢者で健康寿命に自信のある人にとっては検討の価値がある
③特別支給の「老齢年金」は本来の年金とは別もので65歳までに
在職中の月額報酬が一定額を超えると支給停止となり、現役で働い
は全額停止となっている人が多い。「離婚分割」は 離婚後2年以内に請求の要あ
り。「合意分割」は全結婚期間が対象、一律50%を上限に分割割
4.少子高齢化対策について
「年金財政」を考える上で「少子高齢化」は以前から判っており、
種々講じられてきた。
①「年齢による経過措置」:「厚生年金」の定額部分の読み替え率
:1.875 ➡78歳で1.000)。「厚生年金」の報酬比例部分の乗率の2
10 ➡ 78歳で7.5) これらの詳細内容は添付「講演資料その3:老齢基礎年金・
老齢厚生年金・遺族厚生年金 早見表(令和6年度)」をご参照下さい。
②特別支給の「老齢厚生年金」の段階的廃止:かって60歳だった
支給開始年齢を引き上げるための経過措置。
③「厚生年金保険料」を2004年から2017年度にかけ、引き
2004(平成4)年度 ➡ 13.58% 、2017(平成29)年度 ➡ 18.30%
④「厚生年金保険」の適用拡大:2022(令和4)年10月まで
の企業を対象にしていたが、2024(令和6)年10月より、5
時間以上の勤労者を対象に適用の拡大措置を講じる。
⑤「高齢者雇用安定法」:2021(令和3)年4月に施行された
を努力義務とする法律の制定。
⑥「積立金 」:年金積立金管理運営独立行政法人(GPIF)
2024(令和6)年度第3四半期の状況は公的年金受給対象者の
金総額は約4倍半規模と堅調。給付財源中の1割に当たる額が積立
れている。
⑦「マクロ経済スライド」:「年金財政」の健全化(100年安心
2004(平成16)年に導入された制度改革案。少子高齢化によ
対応し「公的年金制度」の持続維持と将来世代への給付水準を確保
口の減少と平均寿命の延びに合わせ、年金額を減額調整する仕組み
フレ期間中は従来の支給水準の方が高く適用が見送られていたが、
年に差が解消されたため 同年度より実施となった。保険料収入の範囲内で給付
されるよう、毎年調整される。
講演報告は以上ですが、参加された皆さんにとって生活がかかった
テーマであり、とりわけ年金の「繰り下げ受給」のくだりでは質問
らうろこ」だったこと、「少子高齢化」の中で年金対策も種々なさ
認識したこと、そして何より、生きている限りは貰い続けられる「
高齢者にとっての「最大の支え=命づな」なのだと、改めて思った 2時間余でした..
「配付資料」と講師近影・講演風景写真数点を添え、ご報告とさせ
以上
早稲田サロン 世話人 岸川 公一、矢吹 淳