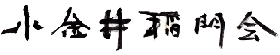さくらの会活動報告(2025.09.28)
「東京ジャーミイ・古賀政男音楽博物館訪問」報告 【さくらの会】
2025年9月28日(日)晴れ
10:30小金井駅改札口に会員9名集合 目的地(代々木上原駅)にむけ出発
代々木上原はどんな町なのかよくわからないという人が多い中、仕事でこの近辺へは度々来ていたという方や、古賀政男博物館ケヤキホールの舞台で歌ったという方もいて、急に町が身近に感じられました。
駅から3分の「古賀政男音楽博物館」へ
古賀政男(明37~昭53)は昭和13年この地に移り住みます。
明治大学在学中にマンドリン倶楽部の創設(大12)に参加。卒業後レコード会社の専属作曲家となり、「影を慕いて」(昭5)、「酒は涙かため息か」(昭6)、「東京ラプソディー」(昭11)、戦後は「悲しい酒」(昭41)など大ヒットを飛ばし、「古賀メロディー」は誰もが耳にしたことのある、昭和を代表する楽曲となります。
昭和33年日本作曲家協会設立、初代会長として翌年日本レコード大賞を制定、昭和53年国民栄誉賞が贈られています。
博物館には大正から昭和の作曲家、作詞家、歌手のレリーフやレコードジャケットなど資料が豊富にあり、検索システムでは8000曲の中から自由に曲を聞くことができます。
歌謡曲の歴史が一望できる貴重な場所であり、またカラオケや自分のCDを作って楽しむこともできます。
併設のケヤキホールでは明大マンドリン倶楽部はじめ、各種コンサートや講座も企画され、将来にひらかれた場所でありたいという古賀氏の思いが伝わっています。
みなさん年代にあわせて足をとめる場所が違い、昔話に花が咲いた様子でした。
そこから歩いて3分「東京ジャーミイ」へ
彩色あざやかな独特の建物(オスマン様式のモスク)が見えてきます。
ロシア革命(1917年)で郷里をおわれたカザン州のトルコ人が東京に移り住み、人々と子供のための宗教教育施設として、日本政府の協力を得1938年(昭13)に「東京回教礼拝堂」をつくります。その後、2000年に現在の「東京ジャーミイ&ディヤーナトトルコ文化センター」が創建されました。
入口右手に広いフリースペースがあり、数人が食事や談話を楽しんでいます。奥にハラルマーケット、個室など、2Fに礼拝所、文化センター(当日は閉館)があります。ジャーミイでトルコランチの予定が、レストランがクローズだったのでコンビニで調達しフリースペースで昼食。
14:30のガイド付ツアーまでの1時間を幹事Yのイスラムクイズで過ごす。これが良く調べられた問題で、全問正解者なし。初めて聞く話や自分の思い違いに「へー」「そうなんだ…」の声、知識の上書き保存ができたかな。
ツアー開始、日曜日のせいか30~40人位の人出です。
1Fで、この建物が造られた時の話から始まる。トルコから多くの資材と人が来て、こだわったので(宗教的に?)完成までに時間がかかったこと、その際の功労者の写真を示し説明。
その後フリースペースに移動し、なぜか、チューリップはトルコが原産だという話になり、現在のチューリップはオランダが品種改良して世界に流通しているもので、原種のチューリップとは姿形が全然違うものだと力説。おそらく茎が短くまっすぐに上を向いていることで何かの暗示なのか、或は最初に発見したもの、手を加えていないことが重要なのか…よくわかりませんでした。
2F礼拝所へ移動 女性は髪を覆います
見学者は後方に座り、礼拝する者は前方に、肩をふれあって1列に並びます。これは神の前には人間はみな平等だということだそうです。
女性には別の礼拝所がありそのわけは、
「気が散るのでいっしょにはやらない。人間ですから当然でしょ」とガイドさん。
大きなドラがなり、礼拝がはじまりました。クルアーン(イスラム教の聖典)の1節が朗々と読み上げられます。
どこにいても1日5回の礼拝はおこなわれています。
東京ジャーミイは年齢や国籍人種にかかわらず訪問できるイスラム教施設で、ここ以外にも文化センターが数か所あり、トルコ料理や語学、書道教室など開催されています。
文明交流の場と冊子にはありましたが、世界でそれを実現してほしいとおもいました。
吉祥寺に戻り「イセヤ」で懇親会。おもしろい一日でした。
(「さくらの会」今中律子)

(↑クリックすると拡大します。)