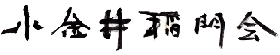「古代メソポタミア」考(投稿論文)
『古代メソポタミア』考

岸川 公一(1972商卒)
ギリシャ語で「メソス」は「間」、「ポタモス」は「河川」を意味し、「メソポタミア」はこれらの合成語で、一般名詞の「川と川の間の地」を意味するそうです。(メゾソプラノの「メゾ」の意味を想起ください)

[出典]メソポタミア-ウィキペディア
メソポタミアに「地方」を付け「メソポタミア地方」と云えば、遠くトルコの山岳地帯を水源とし、シリア高原を経て、イラクの沖積平野をペルシャ湾を目指して流れる、チグリス川とユーフラテス川にはさまれた一帯(現在のイラク共和国と国土的に重なる地域)を指す、固有名詞となります。
この両大河にはさまれた「メソポタミア地方」こそ、「世界四大文明」のひとつ、「メソポタミア文明」の先駆をなし世界で最も早く文明が誕生したとされる、「シュメール文明」発祥の地なのです。
メソポタミア地方は大きく分けて北部地域を「アッシリア」地方、南部地域を「バビロニア」地方と呼びます。更に、南部バビロニア地方は、バグダッド周辺を含む北部地区を「アッカド」地方と呼び、筆者が今から四十年前のイラン・イラク戦争の勃発時(1980年9月)まで足掛け三年間、滞在した、バスラ郊外の肥料製造プラント工場のある、ペルシャ湾に近い南部地区一帯を、「シュメール」地方と呼びます。
紀元前8000年頃の新石器時代にはメソポタミア地方で原始的な農耕が始まっていたとされていますが、紀元前5000年代に入ると、シュメール人の先住民族に当たるウバイド人がバビロニア地方一帯に定住して村落を形成し、初歩的な灌漑(かんがい)農耕を行なうなど、都市文明化の兆しがみられていました。 【ウバイド文化期】
紀元前4000年代の初め、バビロニア地方に「シュメール文明」の担い手となる(一説では宇宙からの飛来説もある)、民族系統不明のシュメール人が入って来て定住します。彼らは多神教を奉じ、アッカド地方、シュメール地方の各地につくられた都市国家(ウルク、ウル、エリドウ、キシュなど)では、それぞれが信奉する都市神をジッグラト(神殿)に祀(まつ)っていました。そして都市化の進展に伴い、増大する人口を賄うため安定した食糧増産に向けた「灌漑農耕の改良・改善」の努力が図られるようになります。

世界遺産ウルのジッグラト
[出典:「イラク ユーフラテスとチグリスの間の地」( Alfred Diwersy 著・独語版)]
シュメール人の創案になる主なものとしては、世界最古の文字とされる「楔形(くさびがた)文字」、バベルの塔で知られる「ジッグラト(神殿or聖塔)の建設」、円周分割の概念から生まれ、現在も広く時間表示などに応用されている「六十進法」、私たちの日常生活に定着している「週七日制」、更には「太陰暦」、「星座命名」などが、挙げられます。
このうち「楔形文字」は、当初シュメール文字で表記されていたのが、シュメール人が紀元前2000年過ぎに歴史の表舞台から去り、これに替わって登場したセム(アッカド語)系民族や、ペルシャ人の諸国家に受け継がれ、マケドニアのアレキサンダー大王がアケメネス朝ペルシャを倒した、紀元前330年までの2千年以上に亘り、メソポタミア地方一帯で公式に使用されていたと云われます。

[出典:楔形文字/ウィキペディア]
「メソポタミア文明」は、シュメール人とセム(アッカド)人の「遭遇」がもたらした文明であり、のちのギリシャ文明とローマ文明の関係にも似ています。あるいはセム民族を、ローマ領内に侵入しローマ文明を吸収し変容させ、ヨーロッパ文明の礎を築いた、ゲルマン民族にたとえることもできます。
ちなみにシュメール人もギリシャ人も、多くの都市国家は形成したものの、「一大帝国」を擁立するまでには至らなかった、という点で共通していたと云えます。
チグリス・ユーフラテス両河の氾濫と 『大洪水伝説』 :

[出典:ユーフラテス川/ウィキペディア]
トルコ東部、海抜1200mの山あいのヴァン湖付近から流れ出す長さ1800kmのチグリス川と、アルメニア山地、アララット山付近の標高3000m級の山岳地帯に水源を持つ、長さ2800kmのユーフラテス川の両大河からの雪解け水は、春先になると、はるかペルシャ湾を目指してメソポタミア地方の沖積平野を下り、農作物の収穫時期と重なる4月頃には下流域のバビロニア地方に達し、押し寄せた河川水の氾濫でこの地方一帯は、甚大な「人的・経済的」な洪水被害にたびたび見舞われてきました。
1920年代に行われた英・米合同調査隊(ウーリー隊)による地層調査結果から、紀元前3500年頃と、紀元前2900年頃に、南部シュメール地方一帯で大洪水があったことが判明しています。特に流れが
急峻なチグリス川流域では、ダムが建造されるようになった二十世紀半ば近くになるまでは洪水被害が頻発していました。
バビロニア地方では、チグリス・ユーフラテスの両河は晩秋の麦の播種期に年間水位が最も低くなったため、この時期に播種作業のため必要とされる農業用水は、両河を取水源とする水路を通じて貯水池から安定的に供給される必要がありました。また、翌春に上流から運ばれて来る雪解け水が多過ぎれば下流域一帯の沖積土で造られた住居は、河川の氾濫によって跡形もなく溶けて流されてしまう恐れがある一方で、雪解け水の量が過少であれば、一帯の旱魃(かんばつ)を招くことにもなります。
このため「水量の管理」は、古代メソポタミア人にとっての「死活」に関わる重要な役務とされ、治水対策はまさに「生きるための術(すべ)」となって、「灌漑技術」向上のための不断の努力が払われてきました。
河川水の量を適正に維持し調整するための、貯水池とをつなぐ水路(運河)の開設・整備と、それに伴う厳密な水量の管理が要求される一方、灌漑水に含まれる塩基物が耕地に集積して生じる「塩害」への対策として、栽培物も次第に小麦に替わって塩害に強い大麦となっていきます。
「灌漑」が計画的に実施され、運河の「浚渫(しゅんせつ)」が定期的に行なわれて初めて緑豊かな耕地が約束されますが、相次ぐ戦乱のさ中にあっては、すべてが「泥沼」と「荒地」に帰してしまいます。
当時の為政者の最も重要な責務は、「政情の安定(外敵からの防衛)と、支配領域内の豊饒とを確たる
ものとし、この世の秩序を糺(ただ)す」ことでした。
この「政情の安定=秩序ある世」の実現のためには「道徳律」が遵守されねばならず、それには社会を組織し管理することこそが肝要で、それが安定した権力基盤につながると確信し実践したのが、セム系のアモリ人が擁立した古バビロニア帝国の、第六代国王で「ハンムラビ法典」の制定者としても著名な、ハンムラビ (在位・紀元前1792~1750)でした。当時、近隣勢力であった、北方のアッシリア帝国やユーフラテス川中流域のマリ王国と軍事同盟を結び、次いでこれらの諸国を併合して帝国の領土をメポタミア地方全域に広げたハンムラビは、「地上に正義を確立する」使命遂行を神から託された者と自らを称して、その「成果」を「ハンムラビ法典」に示したと、伝えられています。

[出典:ハンムラビ王(左)太陽神(右)/ウィキペディア]
古代メソポタミアの人々は、頻繁に発生する両河の氾濫や旱魃が、河川を司(つかさど)る水神 エンキ
(=シュメール語、アッカド語ではエア)が人々に科する懲罰であると考え、その怒りを鎮めるため、ジッグラトにエンキ(エア)神を祀って祈祷を行ない、併せて毎年の豊饒を祈願した、と伝えられています。
そして、これらの云い伝えがベースとなって、遠くシュメールの時代から伝承されてきた「大洪水伝説」が神話の形で、粘土板に書き遺(のこ)されていきます。
古くはシュメール地方北部の宗教都市ニップルの史跡から出土した、古バビロニア帝国初期のものとされる、「大洪水伝説」にまつわる、シュメール語版の粘土板。 (紀元前1800年頃)
時代が下って、アッシリア帝国最後の王都となった、ニネヴェのアッシュール・バニパル王が建造したと
される、「大図書館」跡から発掘された、粘土板にアッカド語で書き遺された「ギルガメシュ叙事詩【標準
版・第11書板】」の中で語られる、「大洪水説話」。 (紀元前1100年頃)
更に時代が進み、新バビロニアによる「バビロン捕囚」(the Exile)の苦難を経て、新バビロニアを滅ぼしたアケメネス朝ペルシャによる捕囚解放令(紀元前538年)で、ヘブライ人が許され、故国パレスチナに戻って以降に編纂を始めたとされる、「旧約聖書」の【創世記】の章で語られる、「ノアの大洪水語」。
(紀元前450年頃)
これらに共通するモチーフは、「堕落し、悪に染まった地上の人間」を大洪水により殲滅(せんめつ)する決定を神々がくだす中で、人間を救おうと考える水神が選ばれた信仰深い家族に密かに計画を明かし、家族は命じられた建造船に乗船し救われる(結果、人間は滅亡を免れる)内容と、なっています。 (ただし、「旧約聖書」中では、唯一神ヤハウェの行為として、書き直されています。)
古来、メソポタミア地方一帯で伝承されてきた「大洪水伝説」は、先人たちが繰り返し経験して来た、両大河による洪水被害の記憶が基となって後世、神話として形づくられたのでした。
【参考】 わが国最大流域面積の利根川(16.8千㎢)に対し、チグリス川(375千㎢)は22倍、ユーフラテス川(765千㎢)に至っては45倍となっており、両河の規模が如何に大きいか、実感されます。
*
古代エジプト人と古代メソポタミア人の『死生観』考 :
定住農耕が始まったとされる紀元前5000年代半ばの古代エジプトでは、夜明けの地平線に一等星シリウスが、太陽と同じ高さに並んで光り始める初日(現在のグレゴリオ暦で、当時の9月9日頃)にナイル川が「増水」し始めることが、経験的に知られていました。
流れが穏やかで、川の氾濫で洪水被害の発生する恐れのないナイル川下流域では、増水の初日から数え、穀類の「播種」は氾濫水が引く120日間が過ぎて、「収穫・刈取り」は240日間が過ぎてそれぞれ開始すればよく、年間を通じて、「洪水対策」としての特別な管理は不要でした。
ナイル川の「規則的な増水・氾濫」は、毎年夏にインド洋で発生するモンスーンがもたらす豪雨で上流から肥沃な土壌を含む大量の濁流が下流域一帯に押し寄せることに因るものでしたが、古代エジプトでは、規則正しく繰り返されるこの事象を基にして一年を増水期(アケト;グレゴリオ暦の9月9日頃~)、耕作期(ペレト;同暦の1月7日頃~)、収穫期(シェムウ;同暦の5月7日頃~)の三期(各120日間+予備5日間)とする、「年間サイクル」が経験則的に確立され、農耕生活が運営されていました。
太陽・シリウス・ナイルの相互関係の詳細な観察結果から、古代エジプトの人々は「年間周期」が(365+1/4)日であることを既に知っていたと云われ(現在との比較で年間時間誤差は僅か11分)、これに基づき作成された「エジプト暦」の運用により、日々の生活を営んでいました。
この「エジプト暦」は「太陽暦」と考えられがちですが、太陽の運行周期に基づき作られた本来の「太陽暦」ではなく、あくまでナイル川を中心として「作物の生育と収穫に必要な一定の周期」に基づき作成された、いわゆる「農本暦」でした。
毎年、定期的に増水し定期的に氾濫するナイルは、そのあとに肥沃な大地を遺し、古代エジプトの人
々の生活を保障したのみならず、後述するように彼らの「死生観・世界観」をも、決定づけたのでした。古代ギリシャ人の歴史家で旅行家のヘロドトス(紀元前485~425)が、いみじくも形容したように、正に「エジプトはナイルの賜物」であり、古代メソポタミア人にとっての「河川」とは、意味合いが著しく異なっていたわけです。
「恩恵」とは正反対の、「破壊」の象徴でもある「大洪水」と云う、当時の人為的な力では如何ともし難い自然(=神)の脅威を、身を以って知っていたシュメール人や、その文化を継承したアッカド人ら、古代メソポタミア世界の人々が抱いていたとされる「死生観」は、「人の命に永遠はあり得ず、死後の世界は真っ暗闇の冥界(死ねばすべてが終わり)」とする、「悲観論」・「諦念観」が強く支配していたと云われ、それはアッカド時代の代表的文学作品とされる「ギルガメシュ叙事詩」(以下に要旨を引用)のなかにも、読み取ることができます。
半神半人のウルクの暴君であったギルガメシュは、「不死の人」を探す旅に出、苦労の末に訪ね当てた当人(ウトナビシュテイム)から、神々による大洪水の企てを水神エアから密かに知らされ船に乗り溺死を免れた体験談を聞かされる。別れ際に「若返りの草」を手に入れるが、帰途それを蛇に盗まれてしまう。 「人間が不死を望むことなど所詮、無理だ」と悟ったギルガメシュは故国に戻り、治政に専心する.
現世の権力者(ファラオ)たちを神々と同等に崇めて祀った「大ピラミッド群」や、アメン神ほかの三神と並んで第19王朝のラメセスⅡ世(紀元前13世紀に在位)を祀った「アブ・シンベル神殿」など、古代エジプト世界での、神々に匹敵する為政者への扱いに比べ、古代メソポタミア世界では、ハンムラビ王やサルゴン大王(アッカド帝国)など、偉大な足跡を遺した錚々(そうそう)たる為政者の王墓跡すら、その所在は今でもはっきりしておらず、代わって神々を祀ったジッグラト跡が各地に見られる事実は、「現世は厳しく、神の力(=自然の脅威)の前に権力者と云えども無力である」と考える、古代メソポタミアの人々が抱いていた「死生観・世界観」と、決して無関係ではないと考えられます。
一方、この考え方の対極にあったのが、古代エジプト人の「死生観」であったと云えます。
彼らの思想は一口で云えば、「現世の肯定・礼賛」(=現世が未来永劫に続くことへの希求)でした。
古代エジプトでは、太陽の沈む西方のかなたに「死者の世界」(=ネクロポリス)があると信じられており、
新王国時代(紀元前16世紀以降)に王都が置かれていたテーベでは、ナイル川をはさみ東側地区を「存命者の世界」(=現世)、また「王家の谷」がある西側地区を「死者の世界」(=来世、ネクロポリス)として、観念的に区分けされていました。
常に自然の脅威に晒されていた古代メソポタミア人とは異なり、「母なる」ナイルのほとりで生まれ育った古代エジプトの人々にとって、現世は居心地よく、別れがたい存在であり、そのため人々の間では「死」は、一時的な肉体と霊魂の分離に過ぎないとされ、霊魂はそのまま生き続けて、以下の「条件」が揃う時に両者は再び「合体」して現世に戻ることができる、と信じられていました。
その条件とは、「住居=墓」、「生活必需品=副葬品」、「肉体=ミイラ」等であり、王墓(ピラミッド)や個人の墓は、これらの条件を備えることで死者の蘇生を念じ、造られたものと云われています。
「自分たちにいつ牙をむくか判らない」チグリス・ユーフラテス両河と常に対峙してきた古代メソポタミアの人々と、「恩恵を施す以外の何者でもない、母なる」ナイルの懐(ふところ)でひたすら「楽観的」心性を育んできた古代エジプトの人々の、それぞれが抱く『死生観・世界観』には、かくも大きな隔たりが生じる結果になった、と考えられます。
お わ り に :
古代メソポタミア世界の人々がその根底に抱いていたとされる、悲観論的『死生観・世界観』は、チグリス・ユーフラテスの両河がもたらす「特殊な自然環境」の下で醸成されたものと考え、同じ時期に、ナイルの恩恵を享受し現世を楽天的に生きたとされる、古代エジプトの人々との対比で考察してみました。多少の個人差は当然あるにしても、古代メソポタミア人の末裔(まつえい)である、現代を生きるイラクの人々の中にそのDNAは今も脈々と受け継がれていると考えると、人間観察にもまた、新たなる興味が湧いてきます...(完)